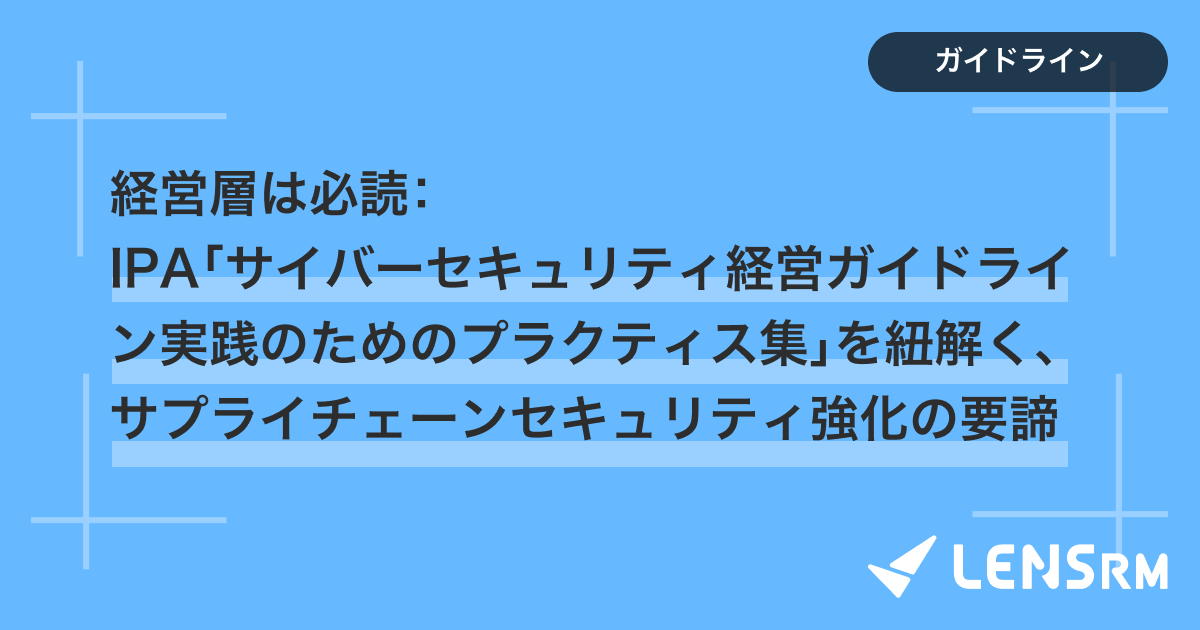経営層は必読:IPA「サイバーセキュリティ経営ガイドライン実践のためのプラクティス集」を紐解く、サプライチェーンセキュリティ強化の要諦
サイバー攻撃が巧妙化・高度化する現代において、企業活動におけるセキュリティ対策は、IT・システム・情報セキュリティ部門だけの課題ではなく、経営そのものを揺るがしかねない重要な経営課題として認識されています。特に、自社のみならず、取引先や委託先といったサプライチェーン全体を巻き込んだセキュリティインシデントが多発しており、その影響は広範囲かつ深刻なものとなる可能性があります。
このような背景から、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、経営者がリーダーシップを発揮してサイバーセキュリティ対策を推進するための「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を策定しました。しかし、ガイドラインだけでは具体的な実践方法が分からないという声も少なくありません。
そこで本記事では、ガイドラインを実践するための具体的な手引書として公開されている「サイバーセキュリティ経営ガイドライン実践のためのプラクティス集」に焦点を当て、その概要と、特に重要となるサプライチェーンにおけるセキュリティ対策、すなわち「委託先管理」の重要性について詳しく解説します。
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン実践のためのプラクティス集」の概要
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン実践のためのプラクティス集」(以下、プラクティス集)は、多くの企業におけるサイバーセキュリティへの先進的かつ実践的な取組事例を収集・分析し、体系的に整理したものです。ガイドラインが示す「重要10項目」を実践する上での具体的な考え方や行動の選択肢を提示し、企業の自主的な取り組みを支援することを目的としています。
サイバーセキュリティ経営ガイドラインとは
まず、土台となる「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」について簡単に触れておきましょう。
これは、経営者がサイバーセキュリティ対策を経営課題として捉え、リーダーシップを発揮することで、企業価値や競争力の向上を目的とした指針です。以下の「重要10項目」で構成されており、経営者が認識すべきこと、そしてCISO(最高情報セキュリティ責任者)等に実行を指示すべきことが示されています。
【経営者が認識すべき3原則】
- サイバーセキュリティは自社の問題と認識し、リーダーシップを発揮する
- 自社のみならず、サプライチェーン全体の対策を推進する
- 平時、有事を問わず、関係者とのコミュニケーションを確保する
【CISO等に実行を指示すべき重要7項目】
- サイバーセキュリティリスクの認識と管理体制の構築
- セキュリティ対策のためのリソース(予算、人材等)確保
- サイバーセキュリティリスクの把握と対策の実践
- インシデント発生に備えた体制の構築
- サプライチェーン全体のセキュリティ対策推進と状況把握
- 情報共有活動への参加を通じた情報収集と共有
- ITシステムだけでなく、制御システムを含めたセキュリティ対策の推進
この中でも特に「8:サプライチェーン全体のセキュリティ対策推進と状況把握」は、近年のリスク動向を鑑みると極めて重要な項目と言えます。
プラクティス集の目的と構成
プラクティス集は、上記ガイドラインをいかにして現場に落とし込み、実践していくかという「How」の部分を補完するものです。先進企業の事例を基に、どのような課題があり、それに対してどのようなアプローチで対策を進めたのかが具体的に記述されています。
主な構成は以下の通りです。
- 第1章 サイバーセキュリティ経営の推進:経営層がどのように関与し、全社的な体制を構築していくかについてのプラクティス。
- 第2章 インシデントに備えた体制の構築:インシデント発生を前提とした、検知、対応、復旧のプロセスや訓練に関するプラクティス。
- 第3章 サプライチェーンセキュリティ対策の推進:本記事の主題である、取引先や委託先を含めたサプライチェーン全体のリスク管理に関するプラクティス。
プラクティス集を読むことで、自社のセキュリティ対策の成熟度を測り、次なる一手を見出すヒントを得ることができます。
関連法規制とサプライチェーン特有のセキュリティ課題
サイバーセキュリティ対策は、単なる企業の自主的な取り組みに留まりません。関連する法規制を遵守する上でも、サプライチェーン全体の管理が求められています。
委託先の監督責任を問う法規制
- 個人情報保護法:個人データの取り扱いを外部に委託する場合、委託元には委託先に対する監督責任が課せられています。委託先が情報漏えいを起こした場合、委託元もその責任を問われる可能性があります。
- 経済安全保障推進法:特定重要物資の安定供給や、基幹インフラの安定的な提供の確保など、経済安全保障の観点からもサプライチェーンの強靭化が求められており、構成要素となる企業のセキュリティ対策は重要な評価項目となります。
これらの法規制は、自社のセキュリティ対策だけでなく、サプライチェーンを構成する委託先や取引先の管理が法的な義務でもあることを示唆しています。
DX推進がもたらす新たなリスク
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、クラウドサービスの利用や外部SaaSの導入、リモートワークの普及などが加速しています。これにより業務効率が向上する一方で、企業の管理すべきIT資産や情報資産は社内ネットワークの境界線を越えて外部に拡大しました。
- クラウド・SaaS利用のリスク:利用するサービス自体の脆弱性や設定不備、サービス提供事業者のセキュリティ体制が、そのまま自社のリスクに直結します。
- リモートワーク環境のリスク:従業員の自宅ネットワークや私物端末(BYOD)の利用など、管理が及ばない領域が増え、攻撃の侵入経路となり得ます。
- サプライチェーンの複雑化:部品供給から製造、物流、販売、システム開発・運用に至るまで、多数の委託先が関与することで、リスク管理の対象は爆発的に増加します。一社でもセキュリティが脆弱な企業があれば、そこが全体の「アキレス腱」となり得ます。
プラクティス集が示す委託先管理とTPRM(サードパーティリスクマネジメント)の重要性
プラクティス集の第3章「サプライチェーンセキュリティ対策の推進」では、こうした課題に対する具体的なアプローチが示されています。これは、近年注目されている**TPRM(Third-Party Risk Management)**の考え方と軌を一にするものです。
TPRM(サードパーティリスクマネジメント)とは
TPRMとは、自社の事業活動に関わる委託先、取引先、供給業者といったあらゆるサードパーティ(第三者組織)がもたらす、情報セキュリティ、コンプライアンス、財務、評判など、様々なリスクを統合的に評価・管理するプロセス全体を指します。
従来の情報セキュリティ監査や委託先評価は、一度きりの評価や定期的なアンケート調査に留まることが少なくありませんでした。しかし、TPRMでは、取引開始前のリスク評価から、契約、継続的なモニタリング、インシデント対応、契約終了時の手続きまで、サードパーティとの関係性全体をライフサイクルとして捉え、継続的にリスクを管理・低減することを目指します。
プラクティス集を活用したTPRM(サードパーティリスクマネジメント)の実践
プラクティス集には、TPRMを実践する上で非常に参考になる事例が多数掲載されています。
- プラクティス3-1:サプライチェーンの可視化
- 課題:二次委託先、三次委託先など、自社が直接契約していない先の状況が把握できていない。
- 実践例:主要な委託先に対して、さらにその先の委託状況に関する報告を求め、サプライチェーン全体の構成を可視化する取り組み。
- プラクティス3-2:委託先選定基準の明確化と契約
- 課題:委託先選定時のセキュリティ評価基準が曖昧。契約書にセキュリティに関する条項が盛り込まれていない、または形骸化している。
- 実践例:セキュリティチェックシートを用いた客観的な評価の実施。インシデント発生時の報告義務や損害賠償責任などを明記したセキュリティ条項を契約に含める。
- プラクティス3-4:委託先の継続的な状況把握とコミュニケーション
- 課題:一度契約すると、委託先のセキュリティ状況を定期的に確認する仕組みがない。
- 実践例:定期的なアンケート調査やヒアリング、現地監査の実施。セキュリティに関する勉強会を共同で開催するなど、平時からのコミュニケーションを強化する。
これらのプラクティスは、まさにTPRMの各フェーズにおける具体的なアクションプランそのものです。しかし、数百、数千にも及ぶ委託先に対して、これらの管理をExcelやメールといった手作業で行うには限界があります。担当者の工数増大、評価の属人化、インシデント発生時の迅速な情報連携の遅延など、新たな課題を生み出しかねません。
サプライチェーンリスク管理の高度化・効率化に向けて
本記事で解説したように、IPAの「サイバーセキュリティ経営ガイドライン実践のためのプラクティス集」は、経営主導でサプライチェーン全体のセキュリティを強化するための羅針盤となる重要な資料です。そして、その実践には、TPRMによる体系的なアプローチが不可欠です。
しかし、その理想的な管理体制を構築し、継続的に運用していくには、専門的な知見と、管理業務を効率化・高度化するための仕組みが求められます。
Lens RMは、まさにこうした課題を解決するために開発された、委託先管理・サードパーティリスク管理ソリューションです。本記事で解説した対応について、お気軽にご相談ください。