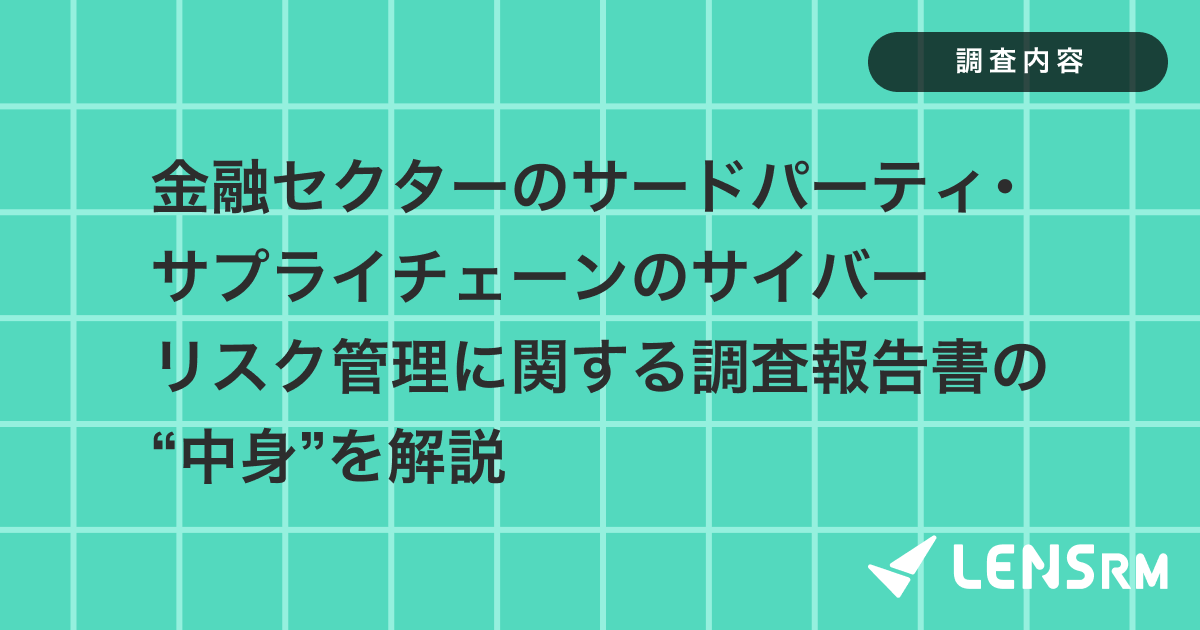金融セクターのサードパーティ・サプライチェーンのサイバーリスク管理に関する調査報告書の“中身”を解説
金融庁は、金融機関の外部委託先やサードパーティに関連するサイバーリスク管理の重要性を鑑み、「金融セクターのサードパーティ・サプライチェーンのサイバーリスク管理に関する調査報告書」を公表しました。本記事では、調査報告書の概要と金融機関におけるサードパーティリスク管理の高度化に向けた示唆について解説します。
調査報告書の背景と目的
1. 調査の背景
近年、金融機関のデジタル化が進展する中、業務やシステムの外部委託が拡大しており、サードパーティへの依存度が高まっています。同時に、サプライチェーンを経由したサイバー攻撃が世界的に増加しており、2020年以降はSolarWindsやLog4jなどのサプライチェーン攻撃が金融セクターにも深刻な影響を与えています。
2. 調査の目的
本調査報告書は、サードパーティやサプライチェーンを通じたサイバー攻撃の脅威が増大する中、米国の大手金融機関における先進的なリスク管理手法を調査し、日本の金融機関への示唆を得ることを目的としています。特に、技術的側面と組織・プロセス的側面の両面からの実践例を収集し、日本の金融機関が参考にできる知見を提供することを意図しています。
サードパーティ・サイバーリスク管理の現状と課題
サードパーティ・サイバーリスク管理の現状と課題には以下のようなものがあります。
1. リスク環境の変化
調査報告書によれば、金融機関を取り巻くサードパーティリスクの環境は、このように変化しています。
- サードパーティの増加と多様化:クラウドサービス、フィンテック連携、ITサービスなど、多様なサードパーティとの関係が拡大
- オープンソースの活用拡大:自社開発システムにおいても多数のオープンソースコンポーネントが利用され、間接的な依存関係が複雑化
- サプライチェーンの深層化:委託先(2ndパーティ)だけでなく、その先の3次・4次の委託先(Nth-party)まで含めたリスク把握の必要性が増大
2. 主な課題
調査で明らかになった主な課題は以下の通りです。
- リソース不足:サードパーティの数に対して、リスク管理を行う人材やツールが不足
- 可視性の欠如:サプライチェーンの深層における依存関係の把握が困難
- 評価の統一性:サードパーティ評価の基準や方法が組織内で統一されていない
- 継続的モニタリングの難しさ:初期評価後の継続的な監視体制の構築が不十分
米国大手金融機関の先進的取り組み(TPCRM:Third Party Cyber Risk Managementの手法)
調査報告書では、米国の大手金融機関が実践している先進的なサードパーティ・サイバーリスク管理(TPCRM:Third Party Cyber Risk Management)の手法が紹介されています。
1. 組織体制の整備
専門チームの設置
米国の大手金融機関では、サードパーティリスク管理を専門に担当するチームや要員を配置し、業務部門を牽制する1.5線的な役割を果たす体制を構築しています。この体制により、事業部門によるサードパーティ選定と、リスク管理部門による客観的評価のバランスが取れた意思決定が可能になっています。
役割と責任の明確化
TPCRM組織内での役割分担も明確化されており、リスク管理フレームワークの設計・維持担当、評価実施担当、技術的評価担当などの専門性に基づいた分業体制が確立されています。
2. 人的リソースの確保と育成
規模に応じた人員配置
数千社のサードパーティを管理するため、TPCRM部門には百人規模でサイバーリスク管理の専門家を配置しています。この規模感は、管理対象のサードパーティ数と、リスク評価の深度に応じて決定されています。
人材育成プログラム
社内トレーニングやメンター制度を活用して人材の質と量を向上させる取り組みが行われています。特に、サイバーセキュリティとリスク管理の両方の専門知識を持つ人材の育成に注力しています。
3. リスク管理プロセスの高度化
リスクベースのアプローチ
評価対象をリスクレベルで分類し、高リスクの評価対象に注力する継続的モニタリングを行っています。リスク評価の頻度や深度は、サードパーティが取り扱うデータの機密性や、提供するサービスの重要度に応じて調整されています。
Nth-partyのリスク評価
必要に応じて4次受け(4thパーティ)以降のリスク評価も実施しています。特に重要なサービスについては、サプライチェーンマッピングを行い、間接的な依存関係まで把握する取り組みが行われています。
業界連携と情報共有
金融機関同士で評価基準や結果を共有する仕組み(Financial Services Information Sharing and Analysis Center:FS-ISAC等)を活用し、評価の効率化と標準化を進めています。
4. 技術的評価の実施
専門チームの設置
自社が使用するソフトウェアの脆弱性を自社で確認する方針の下、技術的評価を実施するチームを持っています。このチームは、セキュリティエンジニアやソフトウェア開発の専門家で構成されています。
高度な評価手法の導入
ソースコードレビューやソフトウェア構成解析(SCA)などの手法を積極的に採用しています。また、ペネトレーションテストやレッドチーム演習などの攻撃シミュレーションも定期的に実施しています。
自動化ツールの活用
継続的なモニタリングのため、脆弱性スキャンや構成解析を自動化するツールを導入し、リアルタイムでのリスク検出を可能にしています。
日本の金融機関への示唆
調査報告書では、米国の事例から日本の金融機関が取り入れるべき示唆として、以下の点が挙げられています。
1. 経営層のコミットメント強化
サードパーティ・サイバーリスク管理を経営課題として位置づけ、十分なリソース(人材・予算・技術)の配分を行うことが重要です。経営層が定期的にリスク状況の報告を受け、必要な意思決定を行う体制の構築が推奨されています。
2. リスクベースの優先順位付け
すべてのサードパーティを同じレベルで管理するのではなく、リスクの高さに応じた管理の深度や頻度を設定することで、限られたリソースの効率的な活用が可能になります。特に、クリティカルなシステムやデータに関わるサードパーティには重点的な監視体制を敷くことが推奨されています。
3. 継続的モニタリングの強化
契約時の評価だけでなく、契約期間を通じて継続的にサードパーティのセキュリティ状況をモニタリングする体制の構築が重要です。脆弱性情報の収集・評価、インシデント対応訓練、定期的な再評価などを組み合わせた多層的な監視体制が推奨されています。
4. 業界協力と標準化の推進
個社での取り組みには限界があるため、業界団体や監督当局と協力し、評価基準の標準化や共同評価の仕組みを構築することが有効です。日本でも金融ISACの活動を強化し、サードパーティリスクに関する情報共有を促進することが期待されています。
金融セクターのサードパーティ・サプライチェーンのサイバーリスク管理は、デジタル化が進む現代において、金融機関の安定性と信頼性を確保するために不可欠な取り組みとなっています。調査報告書で示された米国の先進事例は、日本の金融機関がサードパーティリスク管理を高度化する上で、貴重な参考となるでしょう。
今後は、以下のような動向が予想されます。
- 規制要件の強化:金融監督当局によるサードパーティリスク管理の要求水準の引き上げ
- 管理ツールの進化:AI/機械学習を活用した自動評価・モニタリングツールの普及
- 業界標準の確立:業界横断的なリスク評価基準やフレームワークの標準化
- サプライチェーン透明性の向上:ソフトウェア部品表(SBOM)の普及による可視性向上
Lens RMでは、金融機関向けのサードパーティリスク管理ソリューションを提供しており、調査報告書で示された先進的な取り組みを実現するためのツールとサービスを開発しています。本記事で解説した高度なリスク管理プロセスの導入や、技術的評価の実施について、お気軽にご相談ください。